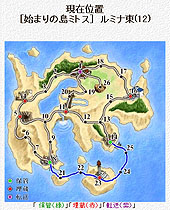配られたカードで勝負する
はじめに
この記事はインターネッツ秘密結社PyspaによるPyspa Advent Calendar 2020の17日目の記事です。
昨日は太一さんのTrain Supply Managerで始める列車自動運行 | さにあらずでした。
さて、このブログは前回の記事も3年前のPyspa Advent Calendarでした。
筆不精なのでPyspa Advent Calendarがないと記事が書けませんね…
前回からの変化としては、この3年でBASEを退職してDX芸人ところてんがやってるNextIntに転職したのですが、その辺りは本質ではないので割愛します。
あ、お仕事は随時募集していますので、お気軽にお声がけください。
nextint.co.jp
麻雀プロになった
去年から麻雀のプロになりました。
なりましたが、麻雀プロってのは名前から想像されるものとは違いそれだけで収入が得られるものではありません。*1
イメージしやすいものだと、社会人サークルが一番近いでしょうか。
そんな訳で僕は趣味で社会人サークルに入ったようなものです。
世の中に麻雀のプロ団体ってのは5つあり、僕はその中の一つ日本プロ麻雀協会に所属しています。
日本プロ麻雀協会にした理由は、縁があったってのと、対局が土日にあるってことでした。
他のプロ団体は平日に対局があることがあるので、なんちゃってとは言え会社員にはハードルが高いのです。*2
強くなるためには
麻雀プロになって思ったことは、麻雀もっと強くなりたい!でした。
では、どうやって強くなれば良いのでしょう?
僕は今まで人生の半分以上の年月をMtGを始めとする対人ゲームに費やして来ました。
その経験上、対戦相手が必要なゲームでは一人で強くなるのに限界があると考えています。*3
自分より劣る人と対戦をしていても強くなるのは難しいのです。
そのため、強くなるためには自分と同程度以上の対戦相手がいるコミュニティに参加する必要があります。
しかし、そういうコミュニティに参加するのは簡単ではありません。
大抵の場合は、自分が参加することでそのコミュニティにもメリットがある必要があるからです。
そのメリットとして一番わかりやすいのは、自分がそのコミュニティの人にとって対戦相手として最低限十分なくらい強いことです。
そこには強くなるためには強い必要があるという矛盾が発生しますし、コミュニティの人にその強さを知ってもらう必要もあります。
とは言え、麻雀プロになったばかりの会社員には難しい話です。
同時期にプロになった人の中では上から数えた方が早い程度には強い自信がありましたが、その程度の人は世の中にたくさんいます。
何より雀荘勤務でもないので知り合いはほとんどいないのです。
ここまでを踏まえて、一番簡単なのは大会で優勝したり上のリーグに所属して名前を知ってもらうことだと考えました。
あくまで僕の現時点の話であって、何が簡単かは人それぞれです。
コミュニティに所属する方法もいくらでもあるので、自分の強みを生かすと良いでしょう。
コミュニケーション能力を生かして仲良くなるのでも良いですし、お金を使うのでも雑用をするのでも方法はたくさんあると思います。
余談ですが、現時点の僕みたいな誰やねんな男性プロを入れてくれる奇特なコミュニティはやじ研*4くらいしか知りません。矢島亨プロには本当に感謝をしています。
麻雀プロになっての立ち位置
プロ団体のメインコンテンツはリーグ戦です。
通年(1年間)もしくは半期(半年)で対局をやって結果に応じて所属するリーグが変動するもので、僕が最初に所属したリーグは一番下のE1リーグでした。
上から数えて11個目のリーグのため、毎回昇級したとしても一番上のA1リーグまでは単純計算で6年半かかります。*5
日本プロ麻雀協会のリーグの数は近年Mリーグの影響からか麻雀プロの増加とともに増えており、僕の入会する1年前はD2リーグでした。*6
それを知ったときはもっと早くプロになってれば良かったと悔やんだものですが、今更言っても仕方ありません。
強くなるための環境を手に入れるためには、リーグを一つ一つ昇っていくしかないのです。*7

関西リーグ
入会して最初のリーグ戦で運良く昇級することができ、E1からD3になりました。
しかし、そこで実感した訳です。一回昇級するのも大変なのに、仮にこのあともストレートで昇級しても6年もかかるのは辛いなって。
なにせ永遠の28歳とは言え僕も良い歳です。20代前半の6年とこれからの6年では、その後に残っている時間が違います。
そこに2020年から関西リーグが新設されるという話がありました。関東からも参加できるように日程も関東のリーグとは被らないようにするとのことでした。
新しくできる関西リーグはABCの3つのリーグで、Aリーグで優勝すると関東のB1リーグに昇級します。

これに特別昇級制度という大会で優勝するとリーグが一つ昇級する制度を加味すると、2回の昇級と1回の特別昇級でB1リーグに昇級することができます。
そのため関西リーグ経由だとA1リーグまで最短で4年です。関東だと1回特別昇級することを考えても5年半です。1年半も短くなりました。
しかも、B1まで7回も勝ち続けないといけないのが3回になります。尚且つ片方がダメだった場合のバックアップとしても機能するのです。
もっとも、そのためには最低でも2年間は年間10回の対局を大阪でしなくてはなりません。
正直とても面倒で、お金もかかります。
しかし、スヌーピーも言ってました。「配られたカードで勝負するっきゃないのさ」って。

画像引用 マイナビ
麻雀が形や打点、速度など手牌の強いところで勝負するのと同じように、現実も自分の強いところで勝負するしかないんです。
どうするか考えるために、自分の強みと弱みを洗い出してみました。
僕の強みは
- 平均的な人より収入がある
- 家族がいなく仕事の融通が利くため時間もある
弱みは
- 年齢が高いため費やせる年月が少ない
それを考えれば、僕が自分の強みを最大限に生かすのは関西リーグにも参加することでした。
弱みである費やせる年月の少なさを強みである金と時間で補うのです。
今年の結果
今年は関東リーグは昇級できませんでしたが、関西リーグでは昇級することができました。
運よく優勝して賞金を3万円もらったのですが、8回*8大阪まで通ったので交通費他で20万以上の赤字です。
ただ関西リーグに通ったことで知り合えた人や名前を覚えてもらうことも増えるなど昇級以外に得たものもありました。
一年間大阪に通ったかいはあったと思っています。

終わりに
ゲームとは違って、現実では自分の手元にある配られたカードは自分の今までの行動の結果引いてきたカードでもあります。
今年引いたカードをを踏まえて、来年もまた手元にあるカードでできることをやっていきましょう。
明日はmoriyoshiさんの多分デスマの話です。楽しみですね!
それでは、良いお年を。
*1:もちろん麻雀プロであることが仕事の一環である方々もたくさんいます
*2:会社員で平日の対局をこなしてる人もたくさんいますし、そういう人は尊敬しています
*3:AIが自分より強い対戦相手足り得る場合はその限りではありません
*4:日本プロ麻雀協会ではリーグ戦の後に現雀王矢島亨プロがやじ研という麻雀プロなら誰でも参加できる勉強会をやっており、僕はそれに毎回参加しています。そこで名前を覚えてもらって、スリアロで放送したやじ研やセットに呼んでもらったりしました。勉強になることだらけなので、参加しないのはもったいないと思ってます。www.youtube.com
*5:特別昇級や2段階昇級などもあるので理論上はもっと短くすることも可能です
*6:現在はE2リーグまであります
*7:日本プロ麻雀協会では上位25%程度が昇級し、下位25%程度が降級します
*8:2日連続の対局が2回ありました
就職してました
この記事はpyspa Advent Calendar 2017の5日目の記事です。
前回もpyspa Advent Calendarでした。
きっとこのブログはきっとpyspa Advent Calendarの更新のためにあるんでしょう。
プライベートのゴタゴタが重な2015年からニートのようなフリーランスのような生活を送っていたのですが、ひと段落ついたため今年の初めから BASE 株式会社 の PAY.JP チームにいます。
仕事始める前は二週間くらいゆるゆるとしてようと思ってたのにしっかり働いてしまっている
— hata hirotaka (@flag_boy) 2017年1月16日
入社して3ヶ月経つのにまだ保険証が来てない
— hata hirotaka (@flag_boy) 2017年4月11日
一番足りなそうなところをやってたら仕様とギョーム知識の人になりつつあって歳を感じる
— hata hirotaka (@flag_boy) 2017年6月1日
決済好きですかって聞かれて好きじゃありませんって答えたし、入社した後も自社のサービス使わずに入社したんですかって煽られました
— hata hirotaka (@flag_boy) 2017年8月1日
ほぼチーム最年長として、こんな感じで昼過ぎまで寝ていたり体調崩したりいらん波風立てたりしながらも働いています。
周りにはpyspaの人をはじめどこかで見たような人も多いですし
8/31をもちまして、今後の成長を祈りつつPAY.JPを卒業しました。丸2年、ミッションクリティカルで刺激的な仕事に関わらせて頂いて本当に感謝しています。簡単にいうとPythonエンジニアが必要です
— moriyoshit (@moriyoshit) 2017年9月1日
半年ちょっとですが「(……神か何かかな?)」って思えるようなもりよしさんと働けたのはとても勉強になりました。
それなりに居心地が良くて多少は貢献もできていると思うので、もうしばらくは働くのではないかと思いますが予定は未定です。
オンラインTCG(トレーディングカードゲーム)の歴史
この記事は pyspa Advent Calendar 2015: 12/6 分の記事です。
ソーシャルゲーム業界の雄Cygamesがshadowverseを発表したことにより話題となっているオンライントレーディングカードゲーム(以下TCG)ですが、その歴史は意外と古くもう15年以上になります。
shadowverseがどのようなゲームを元に作られているのか、Cygamesが今まで作ってきたようなソーシャルゲームとは違うオンラインTCGの歴史を最初期から現在に至るまで順を追って見て行きましょう。
全てはここから始まった (MAGIC: The Gathering)
オンラインTCGの歴史と言いつつ一番最初に取り上げるのはMAGIC: The Gatheringです。
1993年に発売されたこのゲームが全てのTCGの元祖であり、発売から20年以上に渡ってTCGの最先端を走り続けています。
1ゲームのプレイ時間は50分と昨今のソーシャルゲームに比べると長いのですが、当時はテーブルトークRPGやボードゲームなどもっと時間がかかるゲームが大半だったので問題にはなりませんでした。
TCGの基本となる要素の全てを作り出したと言っても過言ではないだけに語れることはいくらでもあるのですが、本題とかけ離れていきそうなので詳しくは述べません。
僕も18年前にMAGIC: The Gatheringに出会わなければ医者にでもなっていたことでしょう。
初めてのオンラインTCG (The Tresure of Genum:トレジャーオブゲノム)
初めて日本でオンラインTCGの名に相応しいゲームが登場したのは1999年。ちょうどNTTドコモがiモードを始めた年であり、今日のMMO(大規模多人数参加型オンラインゲーム)の原型を作ったEverQuestが発売された年でもあり、まだインターネットが一般家庭に普及する前でした。
そんな1999年に開始されたトレジャーオブゲノムはデッキを組んで地図上のルートを決めると後は自動で移動したり戦闘したりしてくれるという仕様のゲームでした。他のTCGのようにプレイングの要素はありませんでしたが、当時の貧弱な環境でもストレスなく遊べることや、1日15分程度で良い手軽さ、漫画雑誌に広告を出したことなどによりユーザー数も多く、攻略本が出たり有志で大会が行われたりと人気をはくしました。
しかし新規プレイヤーを呼び込む有効な施策がなかったことや魅力的な要素の追加がされず既存プレイヤーも離脱を招いたことなどにより、2000年を過ぎた頃から下火となり2008年にはサービスが終了しています。
オンラインでも現実と変わらないTCGを (MAGIC ONLINE)
TCGはリアルでやるものだった2002年にMAGIC: The Gatheringを発売しているWizards of the CoastがMAGIC ONLINEを開始しました。
これは現実のMAGIC: The Gatheringをそのままオンラインで行おうという実際に紙のTCGを発売している会社にしかできない何を考えているのかよくわからないゲームでした。
現実と等しいパックの価格、デジタルなカードを紙のカードと交換することよりその価値が担保されるシステム、トレード機能の実装など昨今のオンラインに特化したTCGでは行えない特有のシステムが盛りだくさんのこのゲームはMAGIC: The Gatheringユーザーの受け皿や入り口として、オンラインに特化できないが故の不自由さや面倒さ(リアルと同じく1ゲーム50分、大会だと3時間から半日以上拘束されます)をはらみつつ今日に至るまで多くのユーザーにプレイされ続けています。
MAGIC ONLINEの成功の後に遊戯王ONLINEなど現実のTCGでオンライン化したものが幾つかあります。
ですが、残念ながらMAGIC ONLINE以外の現実のTCGをオンラインでもやる取り組みは成功していません。
またそれらのゲームも紙のカードとの交換などのシステムは採用していなかったということがいかにMAGIC ONLINEが特異かということを物語っています。
なお最近は紙のTCGにQRコードを付与することにより紙のカードをデジタルでも扱えるオンラインTCGが出て来ているのですが、そもそもそれらのTCGは現実のカードの売り上げがいまいちなのでオンラインと紙を共通にすることに意味があるのかどうかはよくわかっていません。
オンライン専用のTCGを行おうとした意欲作(Alteil - 神々の世界『ラヴァート』年代記)
MAGIC ONLINEによりオンラインTCGと言っても現実のTCGをオンラインでやるものだと思われていた2003年にAlteil - 神々の世界『ラヴァート』年代記はサービスを開始しました。
カードを引かずに最初から全てのカードが(条件さえ整っていれば)使用可能なデッキ、毎ターン増えるリソース、ランダムな要素がふんだんに含まれるカードなど、現実のTCGでは行えないようなデジタルならではの要素が満載で、オンラインに特化したTCGというもののあり方を最初に示したゲームとなっていました。
また1ゲームにかかる時間も10分から20分とソーシャルゲームと比べるとまだ長いですが、オンラインゲームとして負担にならない程度の時間となっています。
Alteil - 神々の世界『ラヴァート』年代記の要素を取り入れたゲームはその後いくつも作られており、最近日本でもリリースされたマビノギデュエルはその直系と言っても良いでしょう。
2008年には【Alteil II 〜銀陽帝大戦】アルテイル2も開始されAlteil - 神々の世界『ラヴァート』年代記と共に現在でもサービスが続けられています。
デッキさえあればTCGたり得るのか(Warstorm)
2008年の秋にデッキを組んだ後は自動で対戦される結果を見るだけという特異なオンラインTCGがサービスを開始しました。
warstorm.comという独自のサイトでサービスをしていたそのゲームは、2010年にFacebookにサービスを移すとFacebook Game流行の波に乗ってユーザー数と売り上げを拡大し一躍人気となりました。
デッキを組んだ後は、毎ターン増えるリソースで手札のプレイできるカードを左から順にプレイされるのを5分程度見てるだけという実にシンプルなゲームでしたが、自分でプレイしている訳ではないのにTCGをやっている感が凄くありました。
ソーシャルゲーム全盛の時代に生まれたゲームだけあって、1プレイの時間も短くチュートリアルも充実しているなど現代のゲーム事情にあった受け入れられやすい作りをしており、TCGをソーシャルゲームっぽくするとこうなるのかと当時は非常に感銘を受けたのを覚えています。
またシステムを簡素にしているだけではなく選んだ陣営ごとに異なる専用のカードや毎ターン最大まで回復し1ずつ増えるリソースなど後述のHearthstoneにも取り入れられている要素がいくつもありました。
そんなWarstormですが2010年に当時飛ぶ鳥を落とす勢いだったzyngaに買収された後、2011年にZyngaの業績不振のあおりを受けサービスを終了しています。
オンラインTCGの集大成(Hearthstone)
WORLD OF WARCRAFT TCGの開発者を中心に当初少人数で開発が始まったHearthstoneは2014年にオープンβテストが開始されると、オンラインに特化したストレスのないゲームシステムとリッチな音声と演出や1ゲームが5〜10分で終わる手軽さ、繰り返されるカードの修正による卓越したゲームバランスで徐々にユーザー数を増やしていきBlizzard Entertainmentの主要なゲームの一つとなりました。
warstormでもあったような丁寧なチュートリアルや、MAGIC: The Gatheringのブースタードラフトをオンライン用に再設計したようなArenaモードなど、今までのオンラインTCGから良いところを抽出した集大成となっていて、その結果2015年現在ではNo.1オンラインTCGの位置を不動のものとしています。
オンラインTCGでありながら運の要素が見た目より全然少ないことも相まってeスポーツとして賞金大会も数多く開かれており、オンラインTCGの歴史を変えたゲームと言っても過言ではないでしょう。
今後もshadowverseを筆頭としたフレーバーだけ変えてシステムを流用したHearthstoneクローンがいくつも出てくることが予想されます。
ソーシャルゲームで言うところのドラゴンコレクションやパズル&ドラゴンズのようなゲームだと思っておけば間違いないです。
まとめ
そんな訳でオンラインTCGの歴史を振り返ってみた訳ですが、これは即ち僕がたどって来たゲームの歴史でもある訳で、こうして並べてみると無駄に費やした時間に感慨深いものがありますね。
今後もたくさんのオンラインTCGが生まれるのでしょうが、何はともあれ興味のある方はHearthstoneをやってみることをお勧めします。
今回の注意事項
- 海外のものはあまり追えていないので抜けている可能性があります。
- 取り上げているのはカードが主体のものですのでカルドセプト等は取り上げていません。
- アーケードカードゲームは僕の守備範囲外なので取り上げていません。
- 画像は各ゲームのサイトから引用させてもらいました。
Python プロフェッショナルプログラミングの第二版(Second Edition)
Python プロフェッショナルプログラミングが3年の時を経て改訂されました。
初版の執筆をした縁でレビューに参加したのですが、全般的に初版に比べてこなれています。
特に @feiz が書き下ろした 11章. 環境構築とデプロイの自動化 がとても良い内容だったので、サーバ構築や自動化を始めようとする人に激しくお勧めします。
あと黒歴史的にクソみたいだった14章のSouthの部分が @hirokiky の手でちゃんとしたDjango Migrationsの内容に変わっていて感動しました。

- 作者: ビープラウド
- 出版社/メーカー: 秀和システム
- 発売日: 2015/02/27
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (4件) を見る
2/27発売らしいです。是非お手に取ってみてください!
猿でもわかるDjango1.7のmigration
さよならSouth
Django1.7からmigrationツールが含まれることになりました。
それにより1.6までは必須なツールだったSouthがお役御免となります。
詳しくはここを読んで欲しいのですが、面倒な方のためにSouthからDjango1.7への移行について簡単に書きます。
Southの場合
アプリケーションを作ったら
$ python manage.py schemamigration myapp --init
アプリケーションを変更したら
$ python manage.py schemamigration myapp --auto
プロジェクト開始時は
$ python manage.py syncdb
migrationの適用は
$ python manage.py migrate
と、幾つか覚えることがあったのですが
Django1.7の場合
アプリケーションを作ったら
$ python manage.py makemigrations
アプリケーションを変更した時も
$ python manage.py makemigrations
プロジェクト開始時は
$ python manage.py migrate
migrationの適用も
$ python manage.py migrate
と、makemigrations と migrate さえすればよくなっています。
こんにちはDjango1.7
makemigrations は schemamigration と違いアプリケーションを指定する必要がなくなりましたし (指定することもできます)
migrate は syncdb をしていない場合やってくれるようになりました。
Southで作成されたmigrationファイルもそのままmigrateできるので、1.6からの移行も問題ありません。
いやー実に簡単ですね。
それでは皆様Django1.7で、よいmigrationライフを。
転職しました
BeProudはとても良い会社でした
BeProudで2年半ちょい働いた訳ですが、3000行超のファイルを書いていたような人間が、他人のコードレビューができるようになるくらいには成長できました。
それもこれも一緒に働いた同僚のおかげですね。
こんな社会不適合社である僕が、素晴らしい同僚と働けた日々は光り輝いていて、共にいられた幸運にとてもとても感謝しています。
そもそもBeProudで働いてなければPyConのスタッフもやっていなかっただろうし、もっと仕事ができないままだっただろうし、色々と感慨深いものです。
ありがとうございました。
転職理由らしきもの
一緒に働いていた人達に不満はありません。
また経営陣(というか社長)に不満がある訳でもありません。
昔の上司で師匠だと僕が勝手に思っている人に戻って来ないかと誘われたのが直接の理由です。
間接的には下世話な話とか受託の話とかもありますけど、ここに書くことでもないので割愛させて頂きます。
現在
そんなわけで12/1からきざしカンパニーで働いています。
相も変わらず東京でPythonを書いているので、今までと変わらずお付き合い頂けると幸いです。
転職して4日が経った
前職は2年半で辞めたので、前職生活の約1/200を現職で過ごしたことになる。
以下略